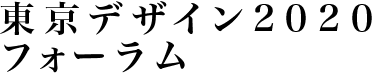亀倉雄策と東京オリンピックのポスター
2020年の東京オリンピックは、ビジュアルデザインの力を一般の人たちに大々的に示すことができる、またとないチャンスです。今日は前回、1964年の東京オリンピックのビジュアルデザインを振り返ってみることにしましょう。
みなさんはそこで重要な役割を果たしたグラフィックデザイナー、亀倉雄策氏をご存知でしょうか。彼は大正生まれで、22歳でデザイン会社の草分けである 「日本工房」に参加し、本格的にデザイナーとして活動を始めました。戦後は焼け跡の銀座に事務所を構え、ニコンのポスターや明治チョコレートの旧パッケージなど、 日本を代表する仕事をする傍ら、日本宣伝美術会(日宣美)や日本デザインセンター(NDC)の創立に参加するなど、デザイナーとして実社会にアクティブにかかわっていました。
1959年には、のちに日本オリンピック委員会(JOC)の委員長に就任する竹田恒徳氏から、オリンピック全体のデザイン顧問を依頼されますが、亀倉氏は 「選ぶ側より選ばれる側になりたい」とこれを辞退します。その代わりにデザイン評論家で、『グラフィックデザイン』誌の編集長だった勝見勝氏を紹介し、 勝見氏がオリンピックの「デザイン懇話会」の座長に就任します。そしてオリンピック史上初の試みとなる、シンボルマークをつくることを決定します。
亀倉氏をはじめ、河野鷹思、永井一正、粟津潔、田中一光、杉浦康平、稲垣行一郎といった活躍中のデザイナーによる指名コンペでしたが、満場一致で亀倉氏の案が選ばれ、これがそのまま第1号の公式ポスターにもなりました。
亀倉氏は「単純に、直接的に日本とオリンピックを感じさせなければならない難しいテーマでしたが、あまりひねったり考えたりしすぎないようにつくった」と 述べています。枠ぎりぎりに赤い円をレイアウトすることで、日の丸でありながら日本的すぎない、しかもデザイナーの個性が出すぎない、とても面白い、いいデザインだったと思います。
亀倉氏は続いて、陸上のスタートダッシュと水泳のバタフライをモチーフとした2号・3号の公式ポスターを手がけます。オリンピック史上初めて写真を用い、50台ものストロボによる高度な撮影技術と、7色刷りグラビア印刷という当時の日本の技術を結集したそのポスターは 世界中に反響を巻き起こし、ワルシャワ国際ポスタービエンナーレの芸術特別賞を受賞しました。
永井一正氏はこのポスターを、戦前から現在まで、日本のグラフィックデザイン史上の最高傑作であると評価しています。とくにスタートダッシュの瞬間を撮影した第2号ポスターでは、背景を黒くするために撮影は夜間の国立競技場で行われ、タイミングが合わないため、30回も40回も撮り直しを続けたと伝えられています。
東京オリンピックの視覚的コミュニケーション
デザイン懇話会では、デザインの制作にあたって共有するべきポリシーが決められています。シンボルマークの一貫した使用、五輪の5色を重点的に用いること、書体を統一し、欧文は「ノイエハースグロテスク(現在のヘルベチカ)」の大文字のみ、和文は写研の「特太ゴシック」を欧文に合わせてやや平体をかけたものを標準書体とする、などです。
開催前年の1963年には、組織委員会が置かれた赤坂離宮の小さな部屋にデザイン室が開設されます。草創期からのデザイナーである原弘氏と河野鷹思氏のほか、実動部隊として指名コンペに参加した永井、田中、杉浦のほか、粟津潔、勝井三雄、道吉剛、横尾忠則といった錚々たるメンバーが参加していました。しかも多くは20代後半から30代前半と、非常に若い人たちでした。彼らが入場券、メダル、ユニフォーム、競技パンフレット、プログラム、施設の標識、案内板など、多様なアイテムをデザインしていました。プログラムは勝井氏、参加記念メダルは、表は岡本太郎氏で裏が田中氏、バッジは河野氏、入場券は原氏の担当といった具合です。
東京オリンピックはアジア初のオリンピックでしたから、その複雑な言語状況を考え、勝見氏はこれもオリンピック史上初となるピクトグラムをつくることを発案しました。
そのチーフは田中氏で、十数人のデザイナーが3カ月かけてつくったといわれます。競技用のピクトグラムは直線や正円など幾何学的なパーツを用いてつくられています。施設用のピクトグラムは、これがなければ会場は大混乱に陥っていたかもしれません(笑)。シャワーのピクトグラムは福田繁雄氏の担当だったそうですが、当時は誰もシャワーを知らず、水が上から流れて体を洗う装置という情報だけで、想像してつくったというエピソードもあります。
オリンピックのピクトグラムは東京大会以降、さまざまなタイプが生まれています。2008年の北京オリンピックは篆刻風、前回のロンドン大会は幾何形態と有機的な曲線がミックスされたものでした。こうしたピクトグラムは、東京大会を機に定着したものです。また、国内外の一般的な公共施設でも、ピクトグラムが使われるきっかけともなりました。
さらに東京オリンピックでは、「デザインガイドシート」がつくられています。これはデザインを制作するうえでのマニュアルとなるはずのものでしたが、度重なる変更があったこともあり、結果的にこれがデザイン室の記録集となりました。
デザインの価値を再認識してもらう機会として
さて、来る2020年の東京オリンピック・パラリンピックについてですが、私は、やはり若い世代が育っていくことができるような機会になればいいなと思っています。
戦前の亀倉氏の世代までは、日本にはグラフィックデザイナーという職業はありませんでした。「図案屋さん」と呼ばれていたんですね。文字やイラストを描いて、しかも必ずしも専門として独立した職業ではなく、画家が内職として行うことも多かったそうです。
ですから1964年の東京オリンピックは、デザイナーが社会的な役割を担うための実験場だったともいわれています。こうして生み出されたデザインワークは国際的にも高く評価され、その後のオリンピックのデザイン・モデルともなっていきました。と同時に日本においては、一般の人が視覚的情報の伝達力の大きさを知る良い機会ともなりました。
しかし当時デザイナーは忙しすぎて、日本橋の上に高速道路が架かることを心配する余裕はなかったのでしょうね(笑)。ですから今度の東京オリンピックでは、デザインのほんとうの価値を発揮して、デザインを再認識してもらえるような契機になれば良いと思っています。
(参考文献:野地秩嘉著『TOKTOオリンピック物語』小学館 2011、『東京オリンピック1964デザインプロジェクト』東京国立近代美術館 2013)
ホーム » Vol.4 »田中佐代子
田中佐代子[筑波大学芸術系准教授 ビジュアルデザイン]