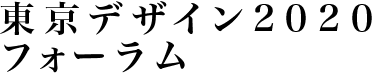「見て楽しむ」発想がない日本のスポーツ
私は、東京キャンパスの夜間の大学院でスポーツマネジメント、とくに推進と振興に関する教育と研究を行っています。以前は日本サッカー協会に勤務し、現在も日本バレーボール協会や日本卓球協会に携わりながら、さまざまなスポーツの振興やスポーツクラブの運営・経営のコンサルタントなども行っています。今日はその視点から、よりスポーツが魅力的になるための環境設計についてお話しします。
まずスポーツイベントとは何かと考えたとき、さまざまな答えがあるでしょうけれど、オリンピックでいうとその正式名称が「The Olympic Games」であるように、その本質のひとつには「ゲーム(game)」ということがあると思います。
その語源は古代サクソン語の「gamen」、つまり一緒にやる(together)という意味の接頭語「ga」と人間「man」から成ることばで、人々が寄り集まり、楽しく喜び合うということですね。つまりゲームは1人でやるものではない。観客もいない試合はゲームじゃない。とすると、われわれはスポーツイベントでゲームということをちゃんと考えているか、反省しなければいけないと思います。
学校の「体育」は自分の体に刺激を与え、自分の体の発展や向上を促す活動ですから、他人の姿を見たり、ともに喜び合ったりということを経験していないですね。体の調子が悪かったりして見学を申し出ると、だいたい先生から冷たく扱われる(笑)。動かない人は体育に参加していない人で、その意味で体育は、あくまでもエクササイズやフィジカル・エデュケーションの発想だということができます。
そのような日本の体育教育の歴史の中でスポーツが捉えられてきた結果、日本の体育・スポーツ施設の3分の2までが教育施設に付随するものとしてつくられる結果となりました。教育施設ですから「する」ことが重要で、「見る」という発想がないですね。中には客席がない施設もあり、飲食、ましてやビールなんてとんでもないという雰囲気です。
「エクササイズ」から「エンターテインメント」へ
同じようにスポーツ選手自身にも、「魅せる」という発想がなかなか生まれていません。多くの選手は観客に見せるというより、自分が一生懸命やるという発想ですから、試合後に観客に手を振ることもしない。お客さんは付属物なわけですね。それは体育教育の中で、見せる/見られることで喜びを分かち合う発想が育ってこなかったからだと思います。
日本のスポーツ施設の多くは「見る」ことより「する」ことを目的に設置されていますから、スポーツを見る・魅せるものにするためには、2020年東京オリンピックを契機として社会運動的に変えていかなければいけないと考えています。
しかしじつは、スポーツ基本法に則って2012年に文部科学大臣が発表したスポーツ基本計画には、「観る人」ということばが初めて登場し、「観る」ことも大切にするよう明文化されています。その結果今後は「観る人」のことを重視したスポーツ施設づくりが進められていくでしょう。
たとえば、スポーツを見ながらの飲食はどうでしょう。日本の多くの体育館は飲食禁止で、しかも土足厳禁です。お客さんにスリッパに履き替えさせたうえに飲食も許さない。もちろんビールもダメ。そんな施設で人が楽しめるでしょうか。
これからのスポーツ施設は、発想をエクササイズやフィジカル・エデュケーションにエンターテインメントを加え、見ることの満足感を高めるデザインが是非必要になってきます。施設の建築やデザインに携わる人には、清く正しく正座をして見るスポーツ施設ではなく、五感を刺激し、見て満足感があふれるような工夫をしていただきたいと思います。
こうした試みは、たとえば新潟県長岡市の駅前にできた「アオーレ長岡」などではすでに始まっています。この複合文化施設には市の議会や行政の窓口があり、カフェ、コンビニがあり、最大5000人を収容できるアリーナが併設されています。客席は壁面に収納できるようになっていて、スポーツもできるしコンベンションにも対応可能になっています。スポーツ施設を単純に教育施設として単体で捉えるのではない考え方が日本でも生まれ始めています。
もちろんアメリカでは、もともとスポーツがエンターテインメントですから、2012年のスポーツ・ファシリティー・オブ・ザ・イヤーを獲得した「バークレーズ・センター」などは、スポーツあり、コンサートあり、バーあり、ラウンジありの楽しいスポーツ・アリーナで、多くの人たちが集まって楽しく過ごせる場所となっています。日本でも東京ドームや福岡ドームはこれに近いと思われますが、公共施設としてはなかなかこうした環境がつくれていないのが現状です。
社会の中で生きる複合的なスポーツ施設の必要
2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けてつくられるものはレガシー(遺産)として開催後も残っていきます。そこでは障害者も含めて、より多くの人びとがスポーツを楽しむ環境を、大会中はもちろん、大会後も視野に入れてデザインできるかどうかが非常に重要になります。
ロンドンの場合は「ロンドン・オリンピックパーク」として現在整備中ですが、一部オープンした場所にはフィットネスクラブやイベントスペースができ、選手村には人が住むなど、オリンピックの印象の残る地域開発が進んでいます。日本も従来の発展途上国型ではなく、こうした先進国型のオリンピックのあり方を学んでいく必要があると思います。
しかしハードができても、喜びや楽しみを共有するソフトがうまく機能しないと結局ハードしか残らなくなります。経営のデザインという視点で、筑波大学には「サービス工学」という学位プログラムも組まれていますが、エンターテインメントとしてのスポーツイベントの経営をどうデザインしていくのか、そういう発想がハードにも組み込まれながら考えられていく必要があるでしょう。
そのためにもスポーツ以外に人は来ないような場所ではなく、複合的な機能を持つことで、常に人が歩いているような施設であることも必要でしょう。これは中心市街地の活性化とリンクして、工場などの大きな建物の跡地をスタジアムにするといったように、すでにアメリカでは行われていることです。中心市街地の活性化、あるいは災害時には避難場所にもなるというような多機能化も必要です。
またエネルギー問題への対応も重要です。ドイツのスタジアムでは、太陽エネルギーを電気に変えるようなパネルがすでに天井に取り付けられ始めています。日本でも、これから自動車のエネルギーとして注目される水素のスタンドがあるとか、太陽光発電で観客が自由に充電できるというような、新しいエネルギーの活用の実例を社会に向かって示すような、そういう柔軟な発想も必要になってくるでしょう。
これからのスポーツ施設は、単にスポーツをするためだけではなく、スポーツを見て楽しみ、なおかつ都市空間や社会の中で、さまざまな機能を担う複合的な生きた施設としてデザインされる必要があるのではないでしょうか。
ホーム » Vol.4 »高橋義雄
高橋義雄[筑波大学体育系 スポーツマネージメント]